「うちの子、もしかしてHSCかもしれない」
そんなふうに思いはじめたのは、
息子が3歳で保育園に入園した頃のことでした。
今でこそ少し笑って話せるようになったけれど
当時は本当に悩んで悩んで、
いろんな葛藤と向き合っていました。
そしてこれからも上手に付き合って
いく方法を伝えなければと
思っています。
うちの息子がHSCかもと疑いはじめたきっかけ
ひとつひとつ乗り越えてきた方法など
当時の記録と共にお伝えします。
HSC(Highly Sensitive Child)とは?
HSCはアメリカの心理学者エレイン・アーロン氏が提唱した
「ひといちばい敏感」という生まれ持った特性。
5人の一人という割合で、生まれつき
よく気が付き深く考えてから行動する
感受性が強く豊かな想像力のある子たちです。
病気でも障がいもない
治すものでもありません。
「自分らしさを伸ばしていけば大丈夫」
そんな風に言われています。
HSCの子に見られる特徴
これはアーロン氏が作ったチェックリストで
13個以上当てはまればHSCかもしれないと言われています。
1.すぐにびっくりする
2.服の布がチクチクしたり、靴下の縫い目や服のラベルが肌にあたったりするのを嫌がる
3.驚かされるのが苦手である
4.しつけは強い罰よりも優しい注意の方が効果がある
5.親の心を読む
6.年齢の割に難しい言葉を使う
7.いつもと違う臭いに気づく
8.ユーモアのセンスがある
9.直観力に優れている
10.興奮した後はなかなか寝付けない
11.大きな変化にうまく適用できない
12.たくさんのことを質問する
13.服がぬれたり砂がついたりすると着替えたがる
14.完璧主義である
15.誰かが辛い思いをしているとに気づく
16.静かに遊ぶのを好む
17.考えさせられる深い質問をする
18.痛みに敏感である
19.うるさい場所を嫌がる
20.細かいことに気づく
21.石橋を叩いて渡る
22.人前で発表するときには知っている人だけのほうがうまくいく
23.物事を深く考える
参考にした本:「HSCの子育てハッピーアドバイス」 作:明橋大二 1万年堂出版
集団生活がしんどかった3歳の春

息子が初めて保育園に通い始めたのは3歳の春。
最初は「慣れるまで時間がかかるのかな」と
思っていたもの…
なかなかクラスに馴染めず、お友達もできず、
先生に困ったことをうまく伝えられない…。
毎朝「行きたくない」と
泣いて訴える日が続きました。
さらに、ストレスからか毎日のように発熱。
保育園に行ってもすぐにお迎え要請の電話がくる…
そんな日々でした。
ある日の突然の出来事と診断まで
そんなある日、
仕事中にかかってきた保育園からの電話。
「今から救急車を呼びます」
急いで駆けつけると、
息子は落ち着きを取り戻していたものの、
保育園で突然倒れてしまったとのこと。
前日体調不良で休んでいた息子は、
「どんぐりを使った製作」の材料を持っておらず、
「自分だけない」ことにパニックになり、
意識を失ってしまったのです。
その後、病院で脳波の検査を行い、
当初は指定難病である
モヤモヤ病の可能性も
指摘され大学病院での精密検査を受けました。
結果、モヤモヤ病ではなかったものの
半年に1回は脳波検査を継続することに。
「HSCという個性かもしれません」
病院の先生に言われたのは
この子の性格ととらえていきましょう。
夫婦でもいろいろ調べていたので
「HSCっていうものを知ったのですが」
と聞くと…先生から
「その可能性は高いと思います」と。
「やっぱり…」といった感じでした。
HSCは、
外部の刺激にとても敏感で、
感情の変化も大きいと言われています。
息子もまさにその傾向があり、
「石橋を叩いても渡らない」タイプ。
慎重で、賢く、繊細でした。
先生が個性というように
HSCという名称がつけられているだけで
病気でもない。
そういった子は今も昔もいるはず。
私も気にしやすい性格だし
その子の気質、個性にあった
生きやすい方法を伝える
経験を通して自信をもって
生活できるようにしていけば
大丈夫ということで
あまり深く考えないようにしました。
当時記録していたもの
はじめて大学病院に受診する際に、
息子の様子を記録し持参した内容です。
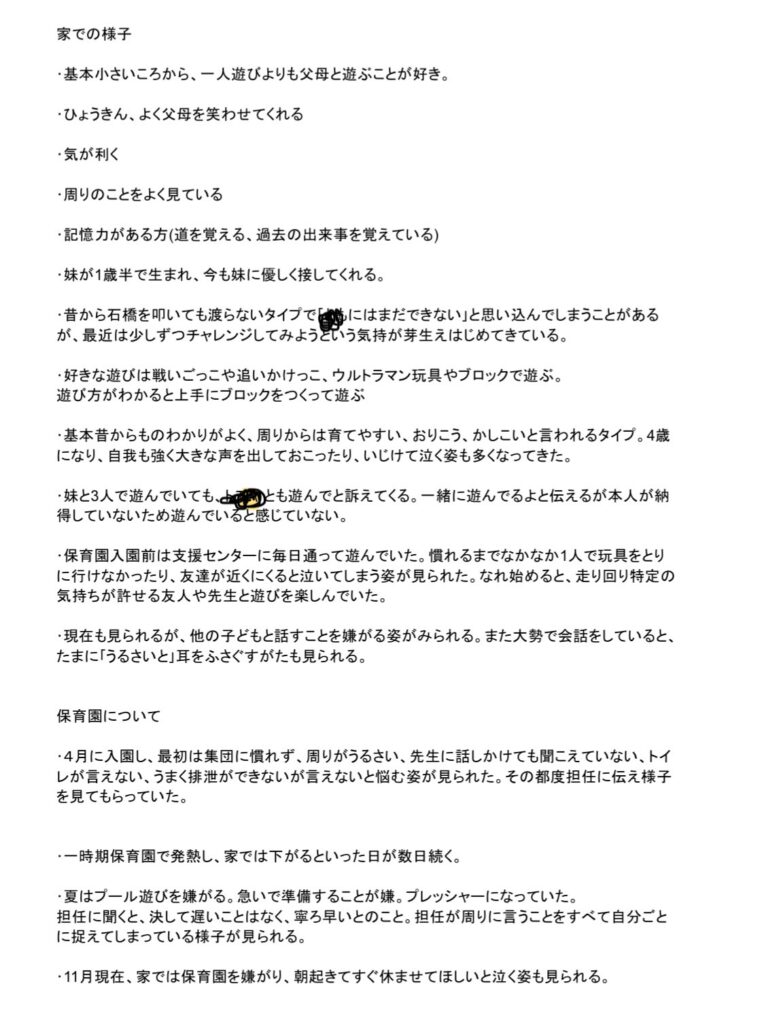
・一人遊びよりも父母と遊ぶことが好き
・ひょうきん、よく父母を笑わせてくれる
・周りよく見ていて気が利く
・記憶力がある(道や過去の出来事を覚えている)
・昔から石橋を叩いても渡らないタイプ
・「僕にはまだできない」と思い込んでしまう
・基本昔からものわかりが良い
・周囲から賢いと言われる
・妹と3人で遊んでいても、僕とも遊んでと訴える。
一緒に遊んでるよと伝えるが
本人が納得していないので遊んでいないと解釈。
・入園前支援センターに毎日通うが慣れるまで時間がかかる
・なれない場所では玩具をとりにいけない
・友達が近くにくると泣いてしまう
・環境に慣れると、特定の友人や先生と遊びだす
・親が他の子どもと話すことを嫌がる
・自分以外が会話をしていると「うるさい」と耳をふさぐ
・洋服のタグや大きさ素材にこだわりが強い
・自分で着脱の難しい衣服は着たがらない
例:
保育園では自分でやることが
多いため洋服を選び実際に着てチェックいする
・集団に慣れるまで時間がかる
・周りがうるさいと話す
・先生に話しかけても気付いてもらえないという
・トイレが言えない、排泄ができないから登園拒否
・保育園で発熱し家で下がるといった日が数日続く
・夏はプール遊びを嫌がる
理由:
急いで準備することがプレッシャーになっていた。
担任に聞くと、息子は決して遅いことはなく、
寧ろ早いとのこと。
担任が周りに言うことをすべて
自分ごとに捉えてしまっている。
・朝起きてすぐ休ませてほしいと泣く
理由:
園庭で1人になってしまう。
僕のところにだれも来てくれない。
先生は僕とは少ししか遊んでくれないが、
他のことはたくさん遊ぶと話す。
・忘れ物があればパニックになる
こんな様子。
パニック症状は
園でしか起きないので
その姿を知っているのは
先生だけでした。
大学病院の先生から言われた内容の記録
・自分の性格を理解し
うまく付き合っていけるよう援助する。
・基本は他の子と同じように関わっていく。
・一番してはいけないことは
「そういう子」「特別扱い」
といったくくりにすること。
・周りを見て敏感になってしまうが
個人を否定するような言葉がけでなければ
時には他の子を強い口調で
叱っていても問題はない。
・慣れで解決することもある
・個性をプラスに捉え、
大人も気にしすぎないことが大切。
保育園と一緒に考えた「安心できる居場所づくり」
何度かパニックで倒れてしまうことが
続いたので、保育園の先生方とも相談して、
事前に不安を減らすための対応を
していただくことになりました。
・これからすることを前もって伝えてもらう
・朝不安を感じる発言があれば事前に担任に伝える
・忘れ物があるときも担任に伝えておく等…
その都度「こんなことまで?」と
思うようなことも共有していくように
していました。
家庭で気をつけたこと
家では、基本普通に過ごし、接し
あれこれ言わず好きに過ごさせていました。
生活のなかで
「こういうこともあるよ」
「困ったときは大人に言えばいいんだよ」と、
いろんなパターンを伝えて、
心の準備ができるようにしていました。
また、お友達と自然に関われるよう、
息子のクラスの仲の良いママ友が
声をかけてくれて
週末遊ぶ機会が増え
少しずつ
「友達と過ごす楽しさ」も伝えていきました。
そして今、少しずつ自信をつけてきた息子

5歳になった今でも、こだわりが強かったり、
洋服のタグや丈を気にしたり、
「これじゃなきゃダメ」が多かったりします。
ここ最近だと
暑いから半袖にしたら?と声をかけると
「先生に半袖でもいいか確認して」と(笑)
いつものことなので
「一緒に聞いてみようか!」
といった感じです
他にもズボンを買いに行くと
絶妙な丈に(股下38.5センチ)に
お直しを求めます(笑)
そして3歳児のときよりも、特徴が顕著にではじめ
当時、当てはまる特徴が10くらいでしたが
今では、ほぼ全て(笑)
ですが今の方が困りごとは少ないようです。
これも4歳が言う?と驚いたのですが(笑)
「保育園で頑張ってるから
家では自由にさせて」と
本人から要望があったので(笑)
やるべきことをやればあとは好きに
過ごしている感じです(笑)
基本前日に自分で持ちものの準備をするのですが
忘れ物をしても「まあいっか先生にいえば」
そんな風に考えられるようにも。
友達ともダイナミックに遊び
公園でも初めて会う子に声をかけ
遊べるようにもなりました。
経験や自信をつけたことで大きく変化している。
とはいえ環境の変化にはまだ敏感。
来年1年生になるので
そこでどうでるかなと思っています。
息子の個性をまるごと受け入れるということ
頻繁に倒れたり、熱を出したりしていた日々。
「このまま保育園生活、
ちゃんと過ごせるのかな」と、
何度も不安になりました。
そして私自身も、仕事を退職して
在宅ワークに切り替えるという選択。
今では倒れることも、不安で
パニックになることもなくなりました。
無理に何かを変えようとするのではなく、
その子のペースに寄り添うこと、あまり気にしすぎないこと
「やりすぎだろ!」と思うことも
笑いにしています♪
それが、
私にできるサポートなのかなと思っています。
最後に
もしこの記事を読んでくださっている方の中に、
「うちの子、ちょっと繊細かもしれないな」
「HSCってなんだろう」
そんな不安や疑問を抱えている方がいたら、
少しでも安心材料になればうれしいです。
大人でも環境の変化は怖いし、不安になる。
それが小さな子どもなら、なおさらです。
焦らず、ゆっくり。
その子にとって「安心できる世界」を
一緒につくっていきたいですね。



